<この記事を読んでわかること>
・脳血栓の原因がわかる
・脳血栓を予防するための食事内容がわかる
・脳血栓を予防するために医療機関を受診することの大切さがわかる
脳血栓は動脈硬化が原因となって生じる病態であり、脳の血管が狭窄することで血栓が形成されて脳梗塞に至ります。
麻痺やしびれなどさまざまな後遺症を残す可能性があるため、できる限り発症を予防することが肝要です。
この記事では、脳血栓の原因から見るリスク要因と予防方法について詳しく解説します。
脳血栓のリスクを高める生活習慣とは?

脳血栓とは、脳の血管で動脈硬化が進展し、血管が狭く・硬くなることで内部を流れる血液が固まり、血栓が形成される病態です。
動脈硬化の原因は主に高血圧であり、ほかに加齢・喫煙・脂質異常症・飲酒・糖尿病などの危険因子が重なることで脳血栓の発症リスクは増大します。
(参照サイト:動脈硬化|厚生労働省)
以上のことからも、脳血栓を予防するためには、日々の生活習慣の中で食事や運動習慣などに注意する必要があり、具体的には下記のような生活習慣が必要です。
- 塩分の摂取量を1日6g未満に抑える
- コレステロールや中性脂肪の過剰摂取は控える
- 糖質の過剰摂取は控える
- カリウムの豊富な果実や野菜を積極的に摂取する
- 過剰な飲酒・喫煙は控える
- 1回30分以上の運動を、少なくとも週に3回以上は行う
上記のような生活習慣を心掛けることが動脈硬化の予防に重要であり、ひいては脳血栓の予防にも重要です。
さらに細かく見ていくと、コレステロールを豊富に含む動物性のレバー、臓物類、卵類や、飽和脂肪酸を豊富に含む脂身の多い肉、鶏皮、バター、ラード、生クリームなどは控えた方がいいでしょう。
また、塩分を控えることは高血圧にとって有用であり、カリウムの豊富な野菜や果実を摂取すると塩分を尿に排出できるため、やはり高血圧予防に有用です。
過度な飲酒は血圧を上昇させる作用があるため、控えましょう。
また定期的な運動は動脈硬化の予防に有用であり、特にウォーキングや水泳などの有酸素運動が効果的なので、生活に取り入れると良いでしょう。
(参照サイト:動脈硬化性疾患の発症を予防するためには?|日本動脈硬化学会)
糖尿病や高血圧が与える影響について
糖尿病や高血圧がなぜ脳血栓にとって良くないのでしょうか?
これは、長期的な糖尿病や高血圧によって血管内皮細胞が損傷し、動脈硬化が進展するためです。
長期的な高血圧や糖尿病は血管内皮細胞を損傷し、その損傷部位から血液中を流れるLDLコレステロールが血管壁内に侵入してしまいます。
血管壁内に溜まったLDLコレステロールはマクロファージと呼ばれる細胞に貪食され、泡沫細胞に変化し、各種サイトカインを放出して血管局所での慢性炎症反応を惹起します。
その結果、血管壁は脆く・硬く変性していき、動脈硬化が進展するのです。
さらにこの状態が進行すると、血管壁内に泡沫細胞が蓄積し、アテロームと呼ばれるコブが形成されます。
このコブは血管内腔を狭小化させ、また肥大化すると突如破裂する可能性もあり、その結果、血管内で血栓が形成される可能性があります。
以上のことからも、糖尿病や高血圧では動脈硬化の進展やアテロームの形成によって脳血栓を引き起こしやすくなるため、注意が必要です。
(参照サイト:アテローム性動脈硬化|MSDマニュアル)
予防のために見直すべき日常習慣と検査の重要性
脳血栓によって脳が虚血に陥れば麻痺やしびれなど神経症状が出現し、日常生活に支障をきたすような後遺症が残ってしまう可能性があります。
そのため、いかに脳血栓の形成を予防するかが重要であり、日常習慣の見直しと定期的な健康診断の受診が肝要です。
普段の食事内容や運動習慣など、日常習慣については先述した通りですが、ほかにも定期的な健康診断の受診や、人間ドックなどで動脈硬化の度合いや生活習慣病の有無を検索することが予防の上で大切です。
医療機関で血圧を測定すれば高血圧はすぐに判定でき、また血液検査で糖尿病・高脂血症も簡単に検索できます。
さらに、動脈硬化の程度を測定する「CAVI検査」や、首の動脈に超音波を当てて血管の性状を調べる頸動脈エコーなど、医療機関での検査では動脈硬化の程度や脳血栓のリスクを詳細に調べることができます。
リスクを把握すれば自身での予防への意欲も高まるため、ぜひこれを機に医療機関にも受診してみると良いでしょう。
まとめ
今回の記事では、脳血栓の原因や予防方法について詳しく解説しました。
脳血栓の最大の原因は動脈硬化であり、動脈硬化は毎日摂取する食事や運動習慣など、日々の生活の質がその形成に大きく関わります。
もし脳梗塞などを発症してしまい後遺症が残ってしまうと、現状ではその症状を根治させる術もないため、やはり予防することが肝要です。
ぜひこれを機に、普段の生活を見直し、気になる方は医療機関の受診を検討しましょう。
一方で、近年では脳梗塞後の後遺症に対する新たな治療法として再生医療が大変注目されています。
ニューロテックメディカルでは、「ニューロテック®」と呼ばれる『神経障害は治るを当たり前にする取り組み』も盛んです。
「ニューロテック®」では、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供しています。
また、神経機能の再生を促す再生医療と、デバイスを用いたリハビリによる同時治療「同時刺激×神経再生医療Ⓡ」によって、これまで改善の困難であった脳梗塞に伴う後遺症の改善が期待できます。
よくあるご質問
- 脳梗塞のリスク要因は?
- 脳梗塞のリスク要因は、主に高血圧や糖尿病・高脂血症などの生活習慣病や、過剰な飲酒、喫煙、肥満などが挙げられます。
また、心房細動や心臓外科手術後など、心臓由来で脳梗塞を発症する可能性もあるため、注意が必要です。 - 脳塞栓症の原因は?
- 脳塞栓症とは、他の部位で生じた血栓が飛んでしまい、脳の血管を閉塞させる病気のことを指します。
特に原因として多いのは心房細動と呼ばれる不整脈であり、これにより心臓内に形成された血栓が脳に飛散することで脳塞栓症を発症します。
(1)動脈硬化|厚生労働省:https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/dictionary/metabolic/ym-082
(2)動脈硬化性疾患の発症を予防するためには?|日本動脈硬化学会:https://www.j-athero.org/jp/general/4_atherosclerosis_yobou/
(3)アテローム性動脈硬化|MSDマニュアル:https://www.msdmanuals.com/
関連記事
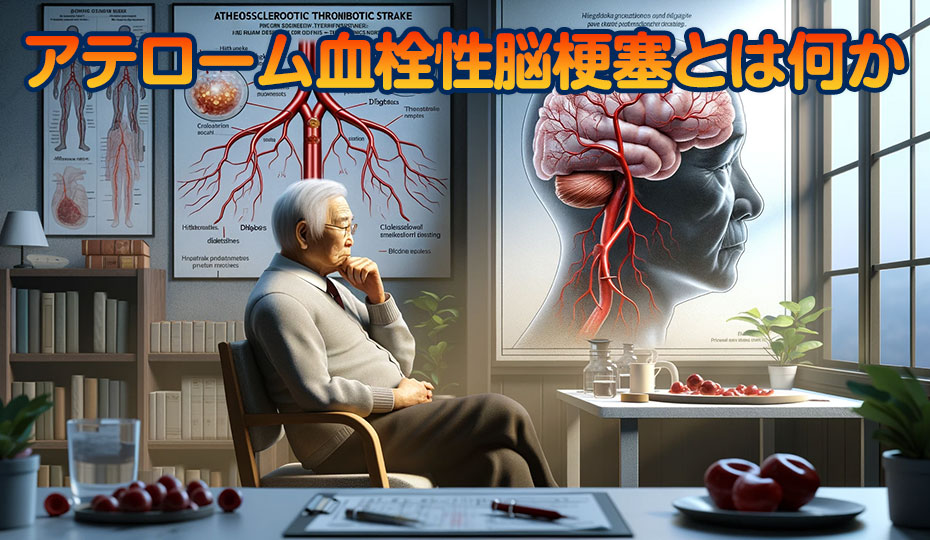
今回はアテローム血栓性脳梗塞とは何かについて解説します。アテローム血栓性脳梗塞は、脳血管内にコレステロールなどの脂質が沈着し、プラークと呼ばれる粥状の塊が形成され、このプラークが破綻することにより、その表面に血栓が形成され、血管が詰まる疾患です。高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙などが原因となります。

高血圧は、脳出血の主要な原因の一つとされています。血圧が慢性的に高い状態が続くと血管に負担がかかり、やがて脆くなった血管が破れてしまうことがあります。本記事では、高血圧と血管の関係、血圧上昇による脳出血のリスク、さらに脳出血を防ぐための対策について詳しく解説します。ぜひ参考にしてみてください。
外部サイトの関連記事:脳幹梗塞と生活習慣病の関係について








