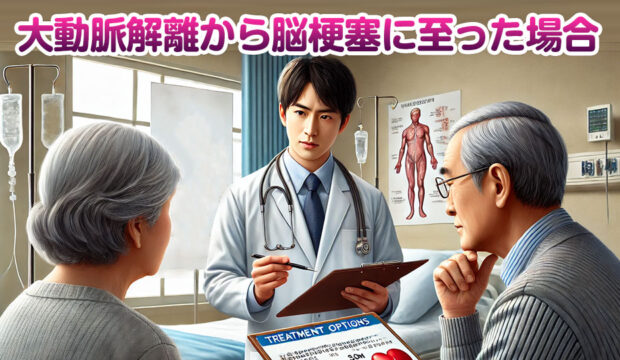・胃ろうとは何か
・胃ろうのメリット、デメリットは何か
・胃ろうは実際に毎日どのように使うのか
胃ろうは、手術で胃や腹壁にあけられた小さな穴のことであり、ここからチューブを通し、直接胃に栄養を注入することができます。
胃ろうは病気や加齢によって口から食事がとれなくなった場合などに適応となります。
この記事では、胃ろうのある日常生活の実際や、胃ろうのメリット・デメリットについて解説します。
胃ろうを持つ患者の日常生活

胃ろうとは、口から十分な栄養を取れなくなった場合に、手術で胃や腹壁に穴を開けて直接管を取り付けて、流動食を入れるための経路として作成された穴のことです。
胃ろうは、脳血管障害(脳卒中)や認知症、その他の病気のために、自分で十分に口から栄養が取れなくなったり、悪性腫瘍などで胃や小腸が閉塞してしまったために減圧をする必要があったりする、といった理由で作られます。
また、自分で食べることはできるものの、むせ(誤嚥:ごえん)を繰り返すような場合にも、胃ろうを作る適応となります。
胃ろうによる経管栄養の利点
胃ろうが与える身体的影響は、経管栄養によって、消化管の運動や消化液の分泌などの消化管の機能を促すことです。
経腸栄養、つまり管を使って栄養を胃に入れる手法には、胃ろうの他にも経鼻胃管(けいびいかん)というものもあります。
胃ろうは、経鼻胃管と比較し、カテーテルが抜けにくく、自己抜去が少なく、そして違和感や不快感が軽減されるという点もポイントです。
また、胃ろうからの栄養を注入しつつ、嚥下訓練も行うことができることもメリットとして挙げられます。
胃ろうによる経管栄養のデメリット
腹部に穴を開けるという手術が必要となりますので、作成した胃ろう周辺に感染を起こすというリスクはあります。
また、胃ろうの手入れを毎日行う必要もあります。
カテーテルトラブルとして、自分で、あるいは何らかの原因によってカテーテルが抜けてしまうこともありえます。
その他、栄養注入剤が濃い・冷たい・注入速度が速いといった理由のために、下痢などが起こるトラブルが起こることもあります。
さらに、胃ろうからの経管栄養でも唾液の誤嚥や嘔吐などが起こりうるので、誤嚥性肺炎のリスクは0にはなりません。
胃ろうを使っている人の日常生活
まずは、経腸栄養を受ける方の上半身を起こし(30度または90度)、姿勢を整えます。
そして、専用の注入容器に栄養剤を入れ、栄養チューブにも栄養剤を満たします。
カテーテルという細い管とチューブを接続し、栄養剤をカテーテルを通じて注入します。
薬も、内容によっては胃ろうから注入することができますが、別々に投与することが大切です。
このタイミングについては、主治医に確認することが必要です。
注入が終わったら、水を注入し、接続チューブ内の栄養剤や薬をきれいに流します。
そして、しばらく上半身を起こしたままにします。これは、食道への逆流を防ぐためです。
最後に、使った器具を洗います。
胃ろうのケアも毎日必要です。
理想は入浴で胃ろうを洗うことですが、できない場合には洗浄を行います。
この際に、カテーテルが抜けていないか、きちんと回るか、胃ろう周囲に感染を疑うような赤みやジクジクがないか、などをチェックします。
胃ろうに関する後悔や悩みの対処法
胃ろうにはメリットもあるのですが、介護の期間などが長引くと、患者の家族の疲れが溜まってしまうこともあるでしょう。
胃ろう造設後も、感染しないように気をつけたり、定期的に交換が必要となったりするために、「胃ろうを作らなければよかった」と後悔することもあるかもしれません。
また、患者の声としても、胃ろうを作れば誤嚥(むせること)が防げると思っていたら、実はそうではなかった、などという思い違いによる後悔が生じることもありえます。
こうした悩みの対処法としては、胃ろう造設をした後のケアの方法についてしっかりと医療従事者などが家族らに説明しておくことや、胃ろうを作った後にも訪問看護師など家族以外の人間が患者や家族らのケアをすることなどが大切だと考えられます。
胃ろうの寿命と交換時期
胃ろうのチューブは半年に1回の交換が目安となっています。
前回交換してからの日数や、次回の交換までの経過や、皮膚の状態などを見て、交換の計画を立てていきます。
もしもチューブが抜けてしまったら、すぐに病院に連絡し、医療的判断を仰ぐようにしましょう。
まとめ
胃ろうは、脳血管障害や認知症、あるいは神経・筋疾患のために、摂食不能、あるいは困難である場合などに作られます。
当院脳梗塞・脊髄損傷クリニックでは、「ニューロテック®」として、脳卒中や脊髄損傷・神経障害などに対する幹細胞治療の基盤特許を取得しており、再生医療の効果を高める取り組みを行っています。
また、リハビリテーション中に幹細胞点滴を行う「再生医療×同時リハビリ™」にも取り組んでいます。
脳卒中などの後遺症としての嚥下障害に対する再生医療についてご興味がある方は、ぜひ一度当院までご相談くださいね。
よくあるご質問
- 胃ろうの問題点は?
- 胃ろうの問題点や欠点としては、胃ろう周辺の皮膚のトラブルが起こらないようにケアをする必要があることや、定期的に医師により胃ろうのカテーテルを交換することが必要であること、さらに、誤って胃ろうを抜いてしまうと、穴が短時間で塞がってしまう可能性があるので、早急に対応しなければならないという点があります。
- 経管栄養 なぜ右側臥位?
- 経管栄養の際、人によっては座った姿勢が難しいこともあります。
そのような場合には、右側を下にした右側臥位や、逆の左側臥位が取られます。
右側臥位の利点は、胃に対して右側に位置する十二指腸が下側に来るので、胃から小腸へと内容物が流れやすいという点です。
胃の動きが弱い方には有効な方法である可能性があります。
<参照元>
胃ろうの適応と管理 | 健康長寿ネット:https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/shumatsuiryou/irou.html
在宅における胃ろう管理の手引き 長崎市訪問看護ステーション連絡協議会:https://nagasaki-nurse.or.jp/nursenet/reference/iroukanri.pdf
Q&A Vol.302 【右?左?】経管栄養中・後の姿勢に関するQ&A 日本離床学会:https://www.rishou.org/for-memberships/qa/qa-vol-302
関連記事

加齢や脳血管障害、パーキンソン病などの神経変性疾患によって、食べ物や飲み物を飲み込む一連の動作に障害が出る状態を嚥下障害といいます。嚥下障害の患者にとって、その家族によるケアは大切になります。今回の記事では、嚥下障害の患者の家族にとって有用な情報として、誤嚥の予防や対策、食事の工夫などについて解説します。
外部サイトの関連記事:脳梗塞後に胃ろうを増設するメリット・デメリット