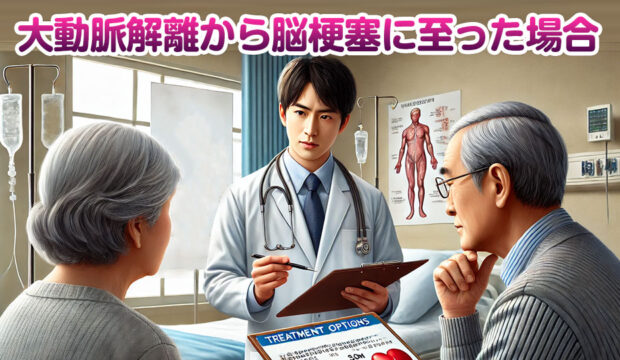<この記事を読んでわかること>
脳梗塞に対する治療法の違いがわかる
t-PAの適応がわかる
脳梗塞に対する新たな治療法がわかる
脳梗塞は日本人の4.3人が発症する病気であり、対応が遅れれば様々な後遺症を残すため、早期発見、早期治療が肝要な病気です。
脳梗塞に対する治療法は常に研究されており、現在ではt-PA、血栓回収術、薬物療法など選択肢も多岐に渡ります。
そこでこの記事では、脳梗塞の治療方法やそれぞれの違いについて詳しく解説します。
血栓溶解療法(tPA)の仕組みと適応条件

脳梗塞にはさまざまな治療方法がありますが、その多くは脳梗塞の原因となる血栓の形成予防や、形成された血栓の増悪予防であり、形成された血栓を直接的に溶かす治療は血栓溶解療法(tPA)しかありません。
血栓溶解療法とは、発症から4.5時間以内の急性期脳梗塞患者に対して、経静脈的にt-PAと呼ばれる薬剤を投与し、詰まった血栓を直接的に溶かす治療方法です。
t-PAは、tissue Plasminogen Activatorの略で、日本語では遺伝子組み換え組織型プラスミノゲンアクチベータと言います。
投与されたt-PAは血液中のプラスミノーゲンと呼ばれる呼ばれるタンパク質を、血栓を溶かす働きを持つプラスミンに変換します。
その結果、プラスミンが血栓の成分であるフィブリンを分解し、血栓を溶解するのです。
この治療は、患者が来院してから少しでも早く行うことが重要であり、発症後4.5時間以内、かつ遅くとも来院から1時間以内に開始することが推奨されています。
一方で、発症後4.5時間以降の場合は、脳梗塞によって組織が壊死している可能性が高く、そこにt-PAを投与して血栓が溶解されると、再開通した際に壊死した組織に血液が流れ込み、かえって出血するリスクが高まります。
これは、老朽化した水道管を久しぶりに使用し、水道管から水が漏れ出すのと同じです。
そのため、t-PAは発症後4.5時間を超えて行うと頭蓋内出血のリスクが高く、4.5時間以内の実施が条件づけられています。
その他にも、下記のような適応条件があります。
| 適応外 |
|---|
|
| 慎重投与 |
|
出血するリスクの高いt-PAは、上記のような厳しい適応条件を満たした患者のみ実施可能です。
血栓回収術が行われるケースとは?
血栓回収術とは、太ももの太い動脈からデバイスを挿入し、梗塞を起こしている脳血管までカテーテルを進めて、梗塞の原因となっている血栓を直接回収する治療法です。
t-PAは適応条件が厳しく、また脳血管の中でも太い血管の梗塞においては再開通率が低いため、t-PA適応外の場合やt-PAと併用する形で実施されます。
脳卒中治療ガイドラインによれば、血栓回収術は下記のような条件を全て満たす急性期脳梗塞患者に対して実施されます。
- 内頸動脈または中大脳動脈M1部の急性閉塞
- mRSスコア0〜1
- 頭部CT・MRIで、ASPECTS6点以上
- NIHSSスコア6点以上
- 18歳以上
上記基準を満たす患者に対し、できればt-PAを行った上で、発症から6時間以内の実施が適切です。
また、脳梗塞の範囲や側副血行の程度によっては24時間以内であれば行うこともあります。
保存療法で行う薬物治療とその役割
上記のような治療の適応外の場合や、適応であっても比較的早期であれば、下記のような薬剤を用いて保存療法が実施されます。
- 抗血小板薬:新規血栓形成予防
- 抗凝固薬:新規血栓形成予防
- フリーラジカルスカベンジャー:フリーラジカル除去による脳保護
- 抗トロンビン薬:血栓形成予防
- グリセオール:脳浮腫の軽減
特に重要なのが抗血小板薬もしくは抗凝固薬による新規血栓形成の予防であり、動脈硬化に伴うラクナ梗塞やアテローム性血栓性脳梗塞には抗血小板薬が、心原性脳梗塞には抗凝固薬が有効です。
再生医療という選択肢
ここまで、脳梗塞に対する様々な治療法を紹介してきましたが、これらの治療はあくまで症状の進行や重症化を予防するための治療であり、一度壊死してしまった脳細胞を元に戻すことはできません。
しかし近年、脳梗塞に対する新たなる治療法として再生医療が大変注目を浴びています。
再生医療では、体外から投与した幹細胞が梗塞によって損傷した脳細胞を再生し、失われた機能の改善が期待されます。
実際に、国内外でも多くの治験が実施され、臨床での実用が今後大いに期待されています。
まとめ
今回の記事では、脳梗塞の治療方法について詳しく解説しました。
脳梗塞に対しては超急性期にはt-PAや血栓回収術などが行われ、その後は脳保護や再発予防のための保存療法が選択されます。
これらの治療法は、どれも一度壊死した脳細胞を再生できるわけではないので、脳梗塞の後遺症が残った場合に改善することは不可能です。
そこで、近年では再生医療による脳梗塞治療が注目されています。
また、ニューロテックメディカルでは、「ニューロテック®」と呼ばれる『神経障害は治るを当たり前にする取り組み』も盛んです。
「ニューロテック®」では、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供しています。
また、神経機能の再生を促す再生医療と、デバイスを用いたリハビリによる同時治療「同時刺激×神経再生医療Ⓡ」によって、これまで改善の困難であった脳梗塞後遺症の改善が期待できます。
よくあるご質問
- 脳梗塞の治療法で第一選択となるのは?
- 脳梗塞の治療法で第一選択となるのは、血栓溶解療法であるt-PAです。
原因となる血栓を溶解することで梗塞を解除しますが、脳出血の発症リスクが高まることから、その適応は厳密に限られています。 - 脳梗塞にエダラボンを使うのはなぜですか?
- 脳梗塞にエダラボンを使う理由は、虚血によって局所的に発生したフリーラジカルを除去するためです。
フリーラジカルは蓄積すると周囲の神経細胞を障害するため、除去することで予後改善を目指せます。
(1)脳卒中治療ガイドライン2021(改訂2023)|日本脳卒中学会:https://www.jsts.gr.jp/img/guideline2021_kaitei2025_kaiteikoumoku.pdf
(2)静注血栓溶解(rt-PA)療法 適正治療指針 第三版|日本脳卒中学会:https://www.jsts.gr.jp/img/rt-PA03.pdf
関連記事

脳血栓とは、脳の動脈に血栓ができて、血流が途絶えることで、脳梗塞を起こす疾患です。動脈硬化が進行すると、血管壁が損傷したり、血管が細くなって血流が悪くなったりすることで血栓ができやすくなります。主な原因は、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病です。
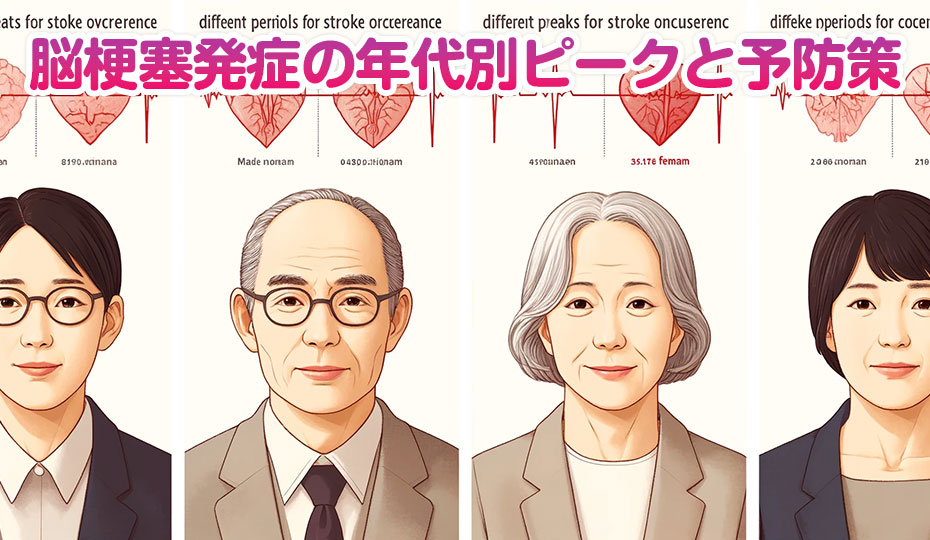
今回は脳梗塞発症の年代別ピークと予防策について解説します。年齢とともに発症が増加しますが、60〜70歳代がピークです。でも、最近では若年層の発症が増加しております。発症は生活習慣と密接な関連があるため、食生活の乱れ、運動不足、喫煙などの習慣を改め、高血圧、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病にならないことが予防策です。
外部サイトの関連記事:脳梗塞予防は玉葱の皮茶と食事と生活改善がカギ