<この記事を読んでわかること>
・顔面神経の走行がわかる
・顔面神経麻痺の原因がわかる
・脳梗塞に伴う顔面神経麻痺の治療法や特徴がわかる
顔面神経麻痺は脳梗塞や外傷・腫瘍・ウイルス感染などさまざまな原因で生じますが、脳梗塞が原因の場合は症状の出方や麻痺の部位が特徴的です。
脳梗塞はその後の予後において早期発見が重要であるため、特徴を知って早期発見・早期治療に努めましょう。
この記事では、脳梗塞による顔面神経麻痺の診断と治療法について詳しく解説します。
脳梗塞による顔面神経麻痺の診断方法

顔面神経とは、顔面の表情筋や唾液・涙の分泌、舌前方⅔の味覚など、さまざまな機能を司る脳神経の1つです。
脳幹を構成する橋と呼ばれる部位に顔面神経核は存在し、大脳皮質からの電気信号はまずこの顔面神経核に送られます。
顔面神経核から長い軸索を伸ばして、顔面神経は小脳橋角部、側頭骨内部の顔面神経管、茎乳突孔を経由して頭蓋骨の外に出て、その後耳下腺内部を貫いて各表情筋に分岐します。
上記のように様々な部位を複雑に走行し、そのいずれかを損傷すれば顔面神経の機能は障害されて顔面神経麻痺を発症するため、さまざまな病気や病態によって顔面神経麻痺は発症しうる症状です。
一方で、脳梗塞に伴い顔面神経麻痺を引き起こす場合、麻痺の出現部位や出方によって他の原因とある程度の鑑別が可能です。
まず、脳梗塞に伴う顔面神経麻痺の場合、麻痺の進行が比較的早く、また顔面神経麻痺以外にも頭痛・意識障害・麻痺やしびれ・構音障害など、さまざまな神経症状を伴います。
ほかに顔面神経麻痺の原因となる脳腫瘍の場合、麻痺の進行は緩徐であり、また外傷や怪我に伴う顔面神経麻痺ならその原因は明白です。
次に、顔面の運動は上下で支配している脳の領域が異なり、顔面の上半分は左右両側の脳で支配されており、顔面の下半分は病変と左右反対側の脳でのみ支配されています。
つまり、脳梗塞によって顔面神経麻痺に陥る場合、顔面の上半分は反対側の脳によって問題なく動きますが、左右反対側の下半分だけは麻痺が生じます。
一方で、外傷や耳下腺炎などによる顔面神経麻痺の場合は、表情筋に分岐する直前の顔面神経が障害されるため、発症した側と左右同側の顔面が上下ともに麻痺するため、そこが脳梗塞との違いです。
以上のことからも、顔面神経麻痺の原因をある程度推察するには、麻痺の出現部位や出方が重要です。
(参照サイト:顔面神経麻痺|日本頭蓋顎顔面外科学会)
脳梗塞部位に応じた治療のアプローチ
上記で示したように、顔面神経の走行は頭蓋骨の外に出てからも、頭蓋骨内部でも非常に複雑です。
大脳皮質から出た運動の指令は大脳内部の神経回路を経由して橋の顔面神経核に送られ、そこから先述したように小脳橋角部や顔面神経管を経由して頭蓋骨の外に出ます。
つまり、大脳はもちろん、橋や小脳などの脳幹で梗塞を起こしても顔面神経麻痺が出現する可能性があるのです。
ただし、脳梗塞の原因部位がどこであっても基本的には治療のアプローチは同じです。
また、顔面神経麻痺が出た場合は原則、原因となる疾患の治療が優先されるため、部位に関わらず脳梗塞の治療が優先されます。
具体的には下記のような治療が行われます。
- 血栓溶解療法
- 抗血小板薬や抗凝固薬の内服
- 血圧や血糖のコントロール
(参照サイト:脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2023〕|日本脳卒中学会)
顔面神経麻痺のリハビリと回復方法
また上記のような医学的治療を行なった上で、並行してリハビリテーションを行うことが重要です。
リハビリテーションを併用することで顔面神経麻痺の改善が期待でき、またその後の機能維持・回復のためにも必要不可欠です。
リハビリを行うことで顔面の筋肉の萎縮や固縮を予防し、顔面のひきつれや不自然な動きを改善することもできます。
具体的には下記のようなリハビリを行います。
- 表情筋を和らげるように手でマッサージする
- 温かいタオルなどで顔の筋肉を和らげる
- 目を見開いて眼輪筋をストレッチする
- 指で口を広げて口輪筋をストレッチする
上記のようなリハビリを、1回10分以上、1日3回以上行うことでより高い効果が得られると考えられています。
(参照サイト:顔面神経麻痺に対するリハビリテーションの進め方|J STAGE)
まとめ
今回の記事では、 脳梗塞による顔面神経麻痺の診断と治療法について詳しく解説しました。
顔面神経麻痺は脳梗塞をはじめとする脳卒中以外にも、外傷や転倒、耳下腺炎、ウイルス感染など、さまざまな原因で発症しうる症状です。
それぞれの原因によっても治療法は異なりますが、特に脳梗塞の場合は対応が遅れれば顔面神経麻痺が後遺症として残りやすいため、注意が必要です。
早期から適切な治療を受け、かつ同時にリハビリテーションを行うことで機能の維持・改善を目指せます。
一方で、近年では脳梗塞後の顔面神経麻痺に対する新たな治療法として再生医療が大変注目されています。
ニューロテックメディカルでは、「ニューロテック®」と呼ばれる『神経障害は治るを当たり前にする取り組み』も盛んです。
「ニューロテック®」では、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供しています。
また、神経機能の再生を促す再生医療と、デバイスを用いたリハビリによる同時治療「同時刺激×神経再生医療Ⓡ」によって、これまで改善の困難であった脳梗塞後の顔面神経麻痺の改善が期待できます。
よくあるご質問
- 顔面神経麻痺の治療方法は?
- 顔面神経麻痺の治療方法は、基本的に麻痺の原因となる疾患の治療となります。
原因がウイルス感染であれば抗ウイルス薬やステロイドの投与、腫瘍であれば手術による切除、脳梗塞であれば血栓溶解療法などが選択されます。 - 顔面神経麻痺のリハビリで禁忌なものは?
- 顔面神経麻痺のリハビリで禁忌は、過剰な筋肉の収縮や電気刺激によるリハビリです。
再生した神経が他の筋肉に分岐してしまい、異常共同運動が起こる原因となってしまうため、控えるべきです。
(1)顔面神経麻痺|日本頭蓋顎顔面外科学会:https://jscmfs.org/general/disease13.html
(2)脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2023〕|日本脳卒中学会:https://www.jsts.gr.jp/img/guideline2021_kaitei2025_kaiteikoumoku.pdf
(3)顔面神経麻痺に対するリハビリテーションの進め方|J STAGE:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jibiinkoka/124/7/124_954/_pdf
関連記事

脳梗塞による顔面神経麻痺は、発症する部位により異なる特徴を示します。脳幹の橋の場合、同側の顔面神経核やその神経線維が障害されるため、末梢性顔面神経麻痺と似た症状が現れます。一方大脳皮質や内包に病変があると、反対側の顔面神経の中枢が影響を受け、中枢性顔面神経麻痺が生じます。この違いは、病変部位の特定に役立ちます。
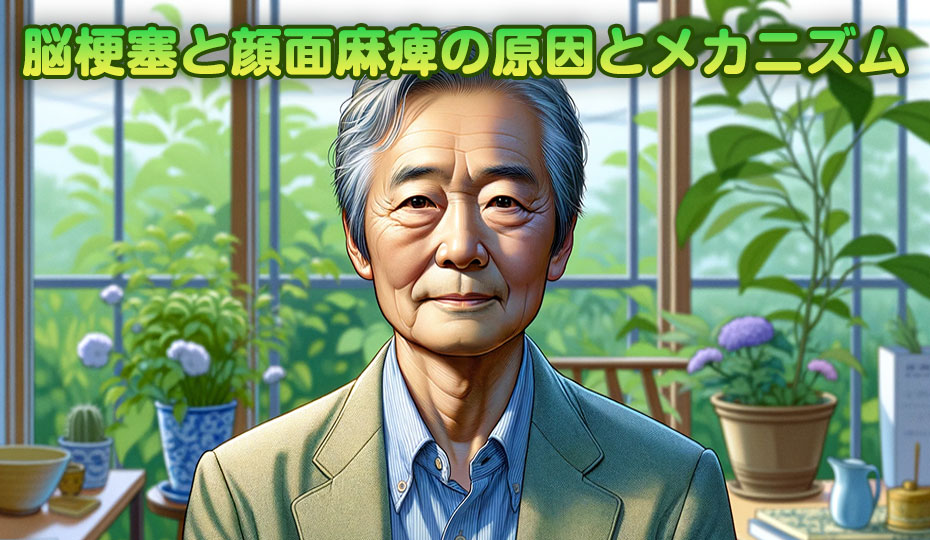
表情を作り出す表情筋の運動は、顔面神経と呼ばれる脳神経によって支配されています。そのため、脳梗塞などによって顔面神経が障害されれば、上手に表情を作り出せなくなり、他にもさまざまな症状を併発し、日常生活に大きな影響をきたします。そこで、この記事では脳梗塞における顔面麻痺の原因やメカニズムについて詳しく解説します。
外部サイトの関連記事:ベル麻痺の基本的な症状とは?








