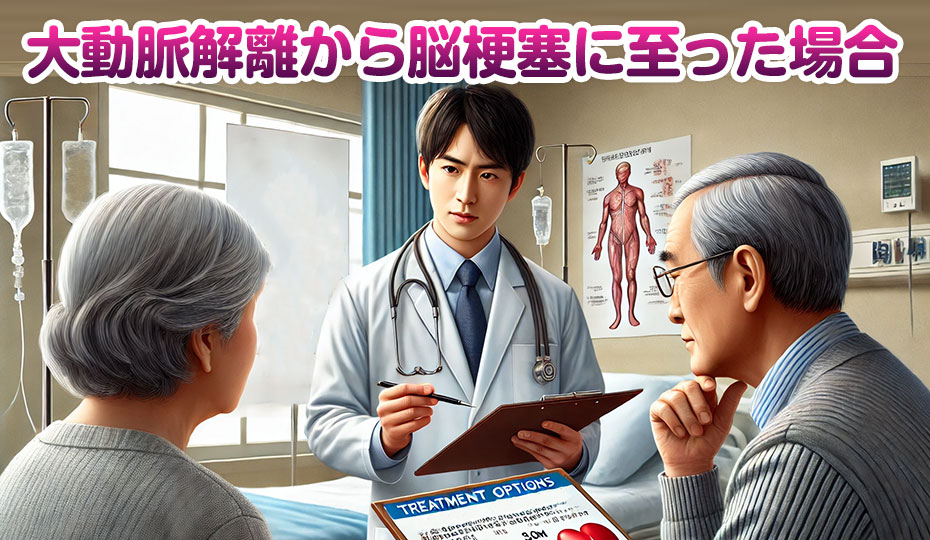<この記事を読んでわかること>
・血圧の左右差とD-dimer値から疑う大動脈解離
・画像診断(CT・MRI)で脳梗塞と解離を特定する方法
・生命を救う緊急手術と脳梗塞への慎重な治療
脳梗塞の症状に加えて、胸痛や背中の痛みなどの大動脈解離に特有な症状が診断の手がかりになります。
確定診断として、症状に加え、CTやMRIなどの画像検査を行い、大動脈解離の場所を特定します。
命に関わる緊急性を要する疾患なので、大動脈解離に対する手術と、脳梗塞の治療を同時に迅速に行う必要があります。
血圧の左右差とD-dimer値から疑う大動脈解離

この記事では血圧の左右差とD-dimer値から疑う大動脈解離について解説します。
Dダイマーとは、血液中の凝固因子であるフィブリンの分解産物で、体内でできた血栓が溶けるときに増加します。
大動脈解離では、血管内膜が損傷することで血栓が出来やすくなるので、Dダイマー値が上昇することがあります。
一方、血圧の左右差が急に起こった場合は、大動脈解離を疑う重要なサインとなります。
大動脈解離は血管内膜に裂け目が入り、血管を傷めることによって、血管を狭めたり、血流を遮断したりする疾患です。
裂け目の位置や大きさによっては、一方の手足に行く血流が低下します。
特に、上行大動脈の解離では右腕の血圧が低下することが多いです。
従って、血圧の左右差とDダイマー値の上昇が同時に認められる場合には、大動脈解離の可能性が高くなります。
さらに、激しい胸痛や背部痛、動悸、呼吸困難、意識障害などの症状がある場合は、大動脈解離を強く疑う必要があります。
これらの所見は、大動脈解離を疑う重要な手がかりですが、確定診断には至りませんので、早急に医療機関を受診して下さい。
画像診断(CT・MRI)で脳梗塞と解離を特定する方法

この記事では、画像診断(CT・MRI)で脳梗塞と解離を特定する方法について解説します。
解離部位の特定は、患者さんの予後にも関連するので、早急の画像診断は重要です。
脳梗塞の画像診断についてです。
CTは数時間から数日経過しないと梗塞巣がはっきりとしないため、急性期の診断では感度がやや劣ります。
でも、出血を伴う脳梗塞や、脳出血と脳梗塞が混在している場合などは、CTでその特徴を捉えることができます。
一方で、MRIは、CTよりも軟部組織の描出に優れているため、CTよりも高感度です。
特に、急性期の脳梗塞では、拡散強調画像と呼ばれる画像を用いると、早期に梗塞巣の検出が可能です。
加えて、脳の血管構造を詳細に観察可能なMRA(磁気共鳴血管撮影)という検査を追加することも可能です。
MRAでは、脳動脈瘤や脳動脈解離などの血管の異常を詳細に検討することができます。
次に、大動脈解離の画像診断についてです。
造影剤を使用したCTやMRAが有効です。
両検査とも、解離による血管内腔の狭窄や偽腔の状態・範囲を詳細に評価できます。
また、MRIのT1強調画像を使うと、解離に伴う血管壁内の血腫を高信号として検出できます。
生命を救う緊急手術と脳梗塞への慎重な治療
この記事では生命を救う緊急手術と脳梗塞への慎重な治療について解説します。
両疾患とも命に関わる緊急性を要する疾患のため、迅速な対応が必要ですが、治療方針は異なります。
大動脈解離によって血管が障害され、血管が破裂すると、大量出血により数分で死亡する可能性があります。
そのため、多くの場合、緊急手術が必要となります。
手術は、損傷した大動脈を人工血管に置き換える人工血管置換術、カテーテルを用いて、ステントグラフトと呼ばれる特殊な人工血管を損傷部位に挿入するステントグラフト内挿術などがあります。
一方、脳梗塞は、時間とともに脳の神経細胞を壊死させる疾患です。
そのため、発症後できるだけ早期に治療を開始することで、脳の損傷を最小限に抑えることが可能です。
具体的には、発症から数時間以内の早期であれば、血栓溶解療法が行われます。
しかしながら、大動脈解離を合併している場合、この治療を行うと、解離が進行したり、血圧が上昇したりするリスクを伴うため、全身状態を検討しながら、慎重な対応が必要となります。
まとめ
今回の記事では、大動脈解離から脳梗塞に至った場合の診断と治療法について解説しました。
脳梗塞は神経細胞を壊死させる疾患のため、後遺症が残ることもたびたびあります。
壊死した神経細胞を蘇させる治療が確立されると後遺症は改善します。
しかしながら、現時点では決め手となる治療方法はありません。
そのため、新たな治療法として、再生医療に期待が持てます。
『神経障害は治るを当たり前にする取り組み』を、ニューロテック®と定義しました。
ニューロテック、脳梗塞脊髄損傷クリニックなどでは、脳卒中・脊髄損傷を専門として、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供しております。
リニューロ®とは、脳卒中や脊髄損傷、神経障害の患者さんに対する『狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療』と定義しております。
具体的には、同時刺激×神経再生医療Ⓡに加えて、治療効果を高めるために骨髄由来間葉系幹細胞、神経再生リハビリ®を併用し、神経障害の更なる軽減を目指しています。
これらの治療法は、不全麻痺による後遺症で苦しむ患者さんに対して期待が持てる治療となるでしょう。
よくあるご質問
- 血圧の左右差と大動脈解離の関係は?
- 大動脈解離が疑われる重要な兆候です。
大動脈解離は、大動脈の内膜が裂けて、血液が血管壁の中に流れ込む疾患です。
この裂け目が血管を狭めたり、血流を遮断したりするため、血圧に左右差が生じます。 - 動脈解離による脳梗塞とはどういうものですか?
- 大動脈という大きな血管が裂ける疾患である大動脈解離が原因で、脳に血液を送る血管が狭くなったり詰まったりして起こります。
動脈解離による脳梗塞は、非常に危険な状態であり、早期の診断と治療が重要です。
・脳梗塞患者の中に急性大動脈解離患者が隠れている~適切な診断を行うための指針を提案~|国立循環器病研究センター:https://www.ncvc.go.jp/pr/release/post_34/
・静注血栓溶解(rt-PA)療法 適正治療指針 第三版|日本脳卒中学会:https://www.jstage.jst.go.jp/
関連記事

脳幹とは呼吸や循環動態・意識など、生命維持にとって必要不可欠な機能をコントロールしている、脳の中でも非常に重要な部位です。そのため、脳幹への血流が途絶する脳幹梗塞に陥るとさまざまな神経症状をきたし、最悪の場合死に至る可能性もあります。この記事では、脳幹梗塞の発症メカニズムや症状の特徴について詳しく解説します。

血管年齢とは血管の動脈硬化の程度を示すものであり、実年齢と比較して高ければ高いほど動脈硬化が進んでいることになります。動脈硬化によって心筋梗塞や脳梗塞などの発症リスクも増加するため、いかに血管年齢を若く保つかが肝要です。この記事では、血管年齢が脳梗塞や心筋梗塞に与える影響について詳しく解説します。
外部サイトの関連記事:背中の痛みが脳梗塞の前兆である可能性