<この記事を読んでわかること>
・水頭症とは、脳脊髄液の循環異常によって脳室が拡大する病気であり、その原因や種類について理解できる。
・水頭症を放置すると、歩行障害や認知機能低下などの症状が現れ、重症化すると生命に関わるリスクがあることがわかる。
・シャント手術をはじめとする治療法や、その成功率、リスクについて知ることができる。
水頭症は、脳脊髄液の循環異常により脳室が拡大する病気です。
水頭症の原因や症状、放置した場合のリスクについて解説し、シャント手術などの治療法やその成功率、リスクについても紹介します。
また、患者の長期的な生活や医療フォローの重要性についても触れています。
水頭症について正しく理解し、適切な対応を知るための参考にしてください。
未治療の水頭症がもたらすリスクとその深刻さ
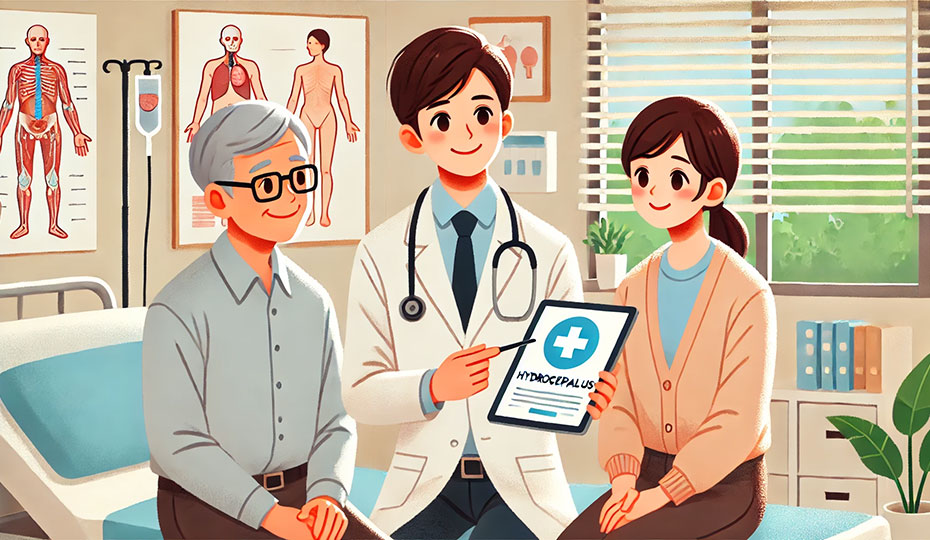
脳や脊髄は、脳脊髄液という液体に浮かんでいる状態です。
そして、脳にはこの脳脊髄液という液体で満たされた部屋があり、これを脳室と呼びます。
脳室には大脳半球の左右にある側脳室、間脳の第三脳室、延髄にある第四脳室の4つがあります。
そして、脳脊髄液はこれらの脳室の脈絡叢(みゃくらくそう)で作られています。
側脳室と第三脳室はモンロー孔、第三脳室と第四脳室は中脳水道でつながっています。
脳脊髄液の産生や循環、吸収のいずれかの異常によって、脳室で拡大してしまい、様々な症状が見られる病気を水頭症といいます。
水頭症には、以下の大きく二つに分けられます。
一つは、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などの脳血管障害の後遺症や、先天性の脳の異常、感染症、脳腫瘍などによって、脳脊髄液の通り道が塞がれてしまった場合です。
これは、非交通性(閉塞性)水頭症と呼ばれます。
もう一つは、脳脊髄液の流れ道などに明らかな狭窄が認められないのにもかかわらず脳室が拡大してしまう交通性(非閉塞性)水頭症です。
その中でも、脳の疾患がない場合には、特発性正常圧水頭症(idiopathic normal pressure hydrocephalus: iNPH)、何らかの脳疾患の後に起こるものを続発性正常圧水頭症(secondary normal pressure hydrocephalus: sNPH)と診断されます。
水頭症を放置しておくと、深刻な症状が現れる可能性があります。
例えば、NPHの場合、歩行障害、認知機能低下、尿失禁という3つの症状がよく知られています。
一方で、先天性水頭症はより大きな問題が生じます。
例えば、中脳水道が狭窄している水頭症や、脊髄髄膜瘤に伴う水頭症の頻度が高いです。
症状は年齢によって異なりますが、新生児や乳児の場合には頭の大きさが大きくなったり、頭の一部が膨らむ症状がみられます。
また、不機嫌になったり活気が不良になったり、あるいは哺乳力の低下もみられます。
症状が進行すると、落陽現象という黒目が下の方による症状や、嘔吐、けいれんもみられます。
年長児になると、頭痛や嘔吐が早い段階からみられます。
これらは頭蓋内の圧力が高まることによりますが、この状態が持続すると、視力低下や失明につながる恐れもあります。
また、うとうとしたりと意識障害がみられ、生命に危険が及ぶリスクもあります。
シャント手術の概要と成功率とリスクについて
水頭症を薬で完全に治すことはまだできません。
水頭症の治療法として代表的なものは、シャント手術です。
これは、交通性水頭症と非交通性水頭症のどちらにも有効です。
シャント手術には、以下の3種類のものがあります。
いずれも、全身麻酔で行います。
なお、歩きにくいという症状で発覚した水頭症の患者さんに対してシャント手術を行なった場合、約80%の方で症状が改善したという研究もあります。
VPシャント
脳室-腹腔シャントのことです。
頭蓋骨に穴を一箇所あけ、脳脊髄液が溜まってしまった脳室に向かって数ミリの管を挿入します。
そして、管のもう一方を、首、胸から腹部まで通し、腸と腸の間に入れる手術です。
脳室に溜まった髄液を、腹腔に逃す手術です。
LPシャント
腰椎-腹腔シャントのことです。
背中側から第2/3腰椎の間の隙間を通し、髄液の溜まっている空間に1ミリほどの管を挿入します。
管のもう一方は、皮膚の下を通って腹部まで通り、腸の間に入ります。
AVシャント
脳室-心房シャントのことです。
脳の骨の一箇所に穴をあけ、ここから髄液が溜まっている脳室に向かって2ミリほどの管を挿入します。
管のもう一方は、頸部の静脈から心房に向かって挿入します。
もちろん、シャント手術には感染などのリスクもあります。
また、脳室を穿刺する際には脳皮質下出血のリスクも伴います。
なお、非交通性水頭症の場合には、神経内視鏡手術が行われることもあります。
代表的なものとして、神経内視鏡的第三脳室開窓術(ETV)という術式があります。
これは、脳の骨に1センチほどの小さな穴を開け、そこから内視鏡を脳室の中に入れ、第三脳室に数ミリほどの穴を開けることで、髄液のバイパス経路を作るというものです。
水頭症患者の長期的な生活と医療フォローアップの重要性
水頭症患者において、特に乳幼児期の水頭症患者ではその後の生活や医療フォローアップの重要性が高まります。
現在の治療成績は向上しているため、80%以上の方で長期生存が可能となってきています。
しかし、精神発達面ではIQ50〜70(軽度知的障害)が約20%、50以下(中等度以上の知的障害)が約20%ほどとなっています。
また、普通学級就学率は約60%とも言われています。
また、身体的な後遺症などが残るケースもあるため、医療的なフォローアップは欠かせないと言えます。
まとめ
今回の記事では、水頭症とはどのような病気なのか、またその予後などについても紹介しました。
特に先天性の水頭症は、治療法の改善によって長期生存が見込める症例も多くみられます。
しかし、脳血管障害の後遺症によって生じた水頭症の場合、その他の後遺症や脳血管障害の再発などによってもその寿命は変わってきます。
後遺症が残ってしまった場合には、リハビリテーションが重要となります。
そのリハビリテーションの効果を高めるために、近年、再生医療の併用が研究されています。
その一例として、ニューロテック、脳梗塞脊髄損傷クリニックなどでは、脳卒中・脊髄損傷を専門として、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供しています。
ご興味のある方は、公式HPをぜひご確認くださいね。
よくあるご質問
- 水頭症を放置するとどうなるのか?
- 水頭症を治療せずに放置すると、脳圧が上昇し、頭痛や嘔吐、意識障害などが生じる可能性があります。
特に乳幼児では頭囲が異常に大きくなったり、発達の遅れが見られることもあります。
進行すると視力低下や失明、最悪の場合は生命に関わるリスクもあります。 - 水頭症の生存率は?
- 水頭症の生存率は治療の有無によって大きく異なります。
適切なシャント手術などの治療を受けた場合、80%以上の患者が長期生存可能とされています。
ただし、知的発達や運動機能に影響が出ることがあり、継続的な医療フォローが重要です。
(1)正常圧水頭症の病態メカニズムとシャント手術.自律神経.2022;59(1):125-131.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/ans/59/1/59_125/_pdf/-char/ja
(2)脳神経外科疾患情報ページ 日本脳神経外科学会:https://square.umin.ac.jp/neuroinf/medical/602.html
(3)正常圧水頭症|東京都健康長寿医療センター:https://www.tmghig.jp/hospital/department/surgery/neurosurgery/nph/
(4)Miyajima M, Kazui H, Mori E, Ishikawa M; , on behalf of the SINPHONI-2 Investigators. One-year outcome in patients with idiopathic normal-pressure hydrocephalus: comparison of lumboperitoneal shunt to ventriculoperitoneal shunt. J Neurosurg. 2016 Dec;125(6):1483-1492. doi: 10.3171/2015.10.JNS151894. Epub 2016 Feb 12. PMID: 26871203.:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26871203/
関連記事

くも膜下出血は、脳の動脈瘤が破裂することなどで起こり、突然の頭痛や意識障害が症状として典型的です。適切な治療によって命をとりとめても、後遺症が残ったり、再出血などのリスクがあったりします。今回の記事では、くも膜下出血の再出血の予後で心配な際の日常生活について解説していきます。

くも膜下出血について、原因から治療まで。脳卒中のひとつであるくも膜下出血は、動脈瘤が破裂して出血した血液が、脳を圧迫することで重篤な状態を起こすものです。突然発症する激しい頭痛という特徴的な症状があり、早急にCTスキャンによる診断、全身状態の安定化、出血のコントロール、そして合併症対策が必要です。高血圧をコントロールし、喫煙や過剰な飲酒を避けることは、重要な予防策です。
外部サイトの関連記事:脳室内穿破とは








