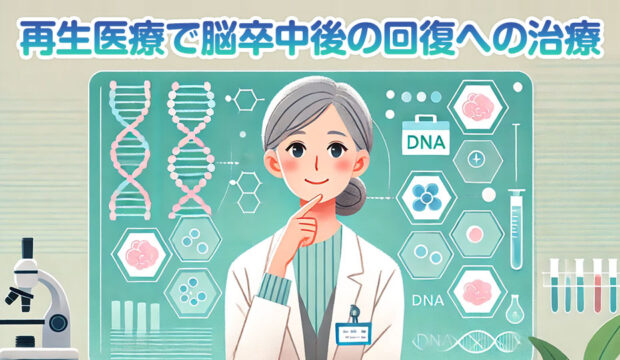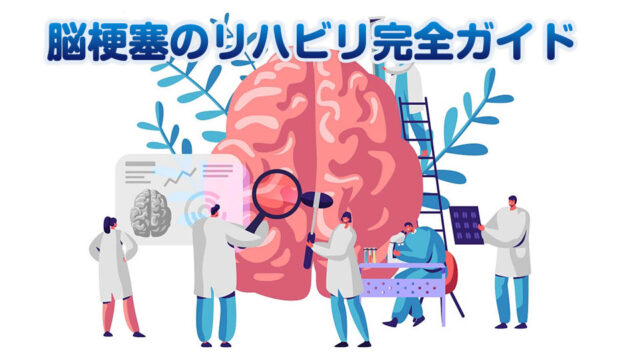<この記事を読んでわかること>
脳梗塞後に生じる筋肉痛や痙縮の原因とその影響がわかる。
中高年・高齢者が実践しやすい筋肉痛対策とセルフケア方法がわかる。
痛みによる生活の質の低下を防ぐためのリハビリとサポート体制がわかる。
脳梗塞後に続く筋肉痛や痙縮は、動作の制限や慢性的な痛みを引き起こし、日常生活の自立や社会参加を妨げる要因となります。
この記事では、痛みや筋緊張が生じる原因をわかりやすく解説するとともに、中高年・高齢者が無理なく実践できる対処法や、生活の質(QOL)を保つためのリハビリの工夫についても紹介します。
筋肉痛が日常生活に及ぼす影響とは?

脳梗塞後に、身体の痛みが続くことがあります。
慢性的な痛みをきたす内科的な疾患として、脳梗塞は重要なものの一つです。
脳梗塞後に慢性的な痛みを感じる方は、約10%ほどとされています。
その痛みの原因として代表的なのは、視床痛というものです。
これは、視床梗塞など、脳の視床という部位を損傷した後に起こる痛みです。
特徴は、体の一部分ではなく、損傷した視床と反対側の広範囲に痛みを感じることが多く、灼熱感、刺すような痛み、骨の芯から疼くような痛みなど、様々な種類の痛みを感じることがあります。
その他にも、脳梗塞後には片麻痺が起こることが多いです。
片麻痺に伴って、二次的な機能障害が起こることも知られています。
例えば、麻痺した側の手足の動きをカバーするために反対の健康な側の筋肉を過度に使ってしまうことによる筋肉痛などがあります。
また、麻痺した側では、関節が拘縮してしまうことなどによる骨や関節の変形に伴い、痛みが生じることもあります。
中高年・高齢者が実践できる筋肉痛対策のポイント

中高年・高齢者が実践できる筋肉痛対策のポイントについてご紹介しましょう。
まずは、麻痺した側の痛みへの対策については、さまざまな方法があります。
麻痺した手足と反対側の痛みは筋肉痛のことが多いと考えられます。
痛みの原因が麻痺した側の動きを庇うために起こっている場合は、正しく身体を使うようにすることが大切です。
特に中高年や高齢者が日常生活で取り組みやすい対策としては、以下のようなものがあります。
- 温熱療法(あたため):血行を促進し、筋肉のこわばりを緩和します。
- 軽いストレッチ:タオルを使った肩回し、座ったままできる足の上げ下げ運動など、負担の少ない方法を選びましょう。
- 栄養管理:筋肉の健康維持には、たんぱく質やビタミンDの摂取も重要です。
また、無理な動作をしないこと、正しい姿勢を意識することも、痛みの悪化を防ぐポイントです。
そのためには、適切なリハビリテーションを受けることが大切になります。
しかし、麻痺した側の手足に痛みがある場合には、神経性の痛みの可能性があるため、きちんと主治医の診療を受け、その他の痛みを除外することも大切です。
生活の質を向上させるためのリハビリとサポート体制
筋肉痛の背後にある「痙縮(けいしゅく)」や「拘縮(こうしゅく)」といった後遺症も、生活の質を左右する要素です。
これらは、脳梗塞などで上位運動ニューロンに障害が起こることで生じ、筋肉が異常に緊張し、硬くなって動かしにくくなる状態です。
痙縮や拘縮に対する治療法には以下のようなものがあります。
- 抗痙縮薬の内服
- フェノール・アルコール注射による神経遮断
- ボツリヌストキシン注射による化学的脱神経
- 外科的手術や装具療法
- 理学療法士によるリハビリテーション
リハビリの内容は、医師・理学療法士・作業療法士など多職種が連携して行います。
急性期のうちから正しい肢位保持や運動療法を取り入れることが、筋緊張の悪化や変形の予防にもつながります。
また、通院が困難な方には訪問リハビリや在宅医療のサポートも有効です。
日々の介助を担うご家族や介護者も、正しい動かし方やケアの方法を学ぶことで、痛みの緩和や再発防止に寄与できます。
また、こうした筋肉の拘縮を予防するためには、脳血管障害の急性期からの対策が必要となります。
脳梗塞などの脳血管障害を発症してまもなくの頃は、筋肉が比較的弛緩、つまりゆるんでいることが多いです。
この時期に、手足を正しいポジションに保つことや、適切な介護・介助をすることによって、正しく筋肉が使えるような状態に戻ることも可能となります。
まとめ
脳梗塞後の筋肉痛は、後遺症の一部として軽視できない問題です。
特に中高年・高齢者にとっては、痛みによる活動量の低下が寝たきりや認知機能低下のリスクにつながる可能性もあります。
そのため、痛みがある場合には放置せず、医療者に相談することが第一歩となります。
そして、医療機関での適切な治療に加えて、自宅でできるセルフケアや、リハビリ、栄養管理などを組み合わせることで、QOLの維持・向上が期待できます。
近年では、神経障害を「治るのが当たり前」にする取り組みとして、再生医療の活用も進んでいます。
例えば、ニューロテック®では、脳卒中や脊髄損傷の患者さんに対し、「狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療」であるリニューロ®を提供しています。
リニューロ®では、同時刺激×神経再生医療®により、損傷部の神経回路を強化・再構築し、さらに骨髄由来間葉系幹細胞の投与や神経再生リハビリ®との併用によって、痛みや運動障害の軽減を目指します。
特に、筋肉痛や痙縮などの後遺症に対しては、早期の神経回路の刺激と再生が重要となります。
本人の努力だけでなく、ご家族・医療者・地域が一体となって支える体制を整えていくこと、そして、新たな選択肢としての再生医療を理解し、活用することが、これからの高齢社会においてますます大切になるでしょう。
よくあるご質問
- 脳卒中による痙縮は筋肉にどのような影響がありますか?
- 痙縮とは、脳卒中後に起こる筋肉の異常な緊張状態で、筋肉が自分の意思とは関係なく強く収縮し続ける現象です。
これにより、関節の動きが制限され、日常生活での動作が困難になったり、痛みや拘縮(関節のかたまり)を引き起こす原因になります。 - 脳梗塞の後遺症で筋肉がつっぱるのはなぜですか?
- 脳梗塞によって運動機能を司る神経回路が損傷されると、筋肉を調整する命令がうまく伝わらなくなります。
その結果、筋肉が過剰に緊張して「つっぱる」感覚(痙縮)が起こります。
これは神経系の障害によるもので、自力では緩めにくいのが特徴です。
(1)全身痛を来たす神経内科疾患.日内会誌.2019;108:2088-2094.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/108/10/108_2088/_pdf
(2)筋緊張のコントロール.関西理学.2003;3:21-31.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkpt/3/0/3_0_21/_pdf
(3)骨格筋量の維持・増加に向けたたんぱく質摂取の重要性 農畜産業振興機構:https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_001867.html
(4)上位運動ニューロンとは 中外製薬:https://with-your-sma.jp/glossary/03_002.html
関連記事
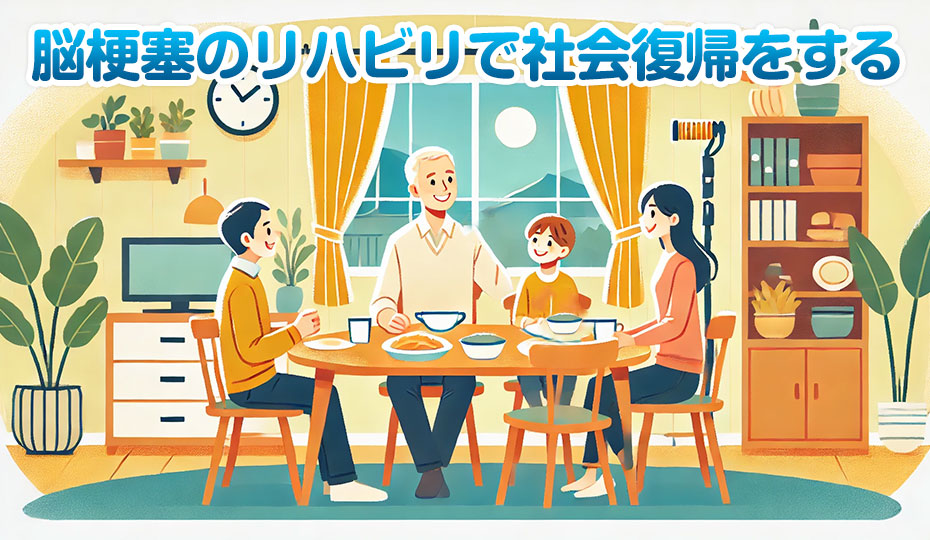
脳梗塞を発症した場合、できるだけ早期からのリハビリテーションの開始が重要とされています。この記事では脳梗塞発症後の段階にそった効果的なリハビリテーションプログラムや家族のサポートが与える影響について、さらに社会復帰を目指すためのステップと活用できる支援制度について解説しています。

頚椎症性脊髄症(けいついしょうせい せきずいしょう)は、加齢に伴う頚椎の変形や椎間板の拡張、靭帯が分厚くなることなどから生じる疾患です。これらの変化により、頚部の脊柱管が狭くなり、そこを通過する脊髄が圧迫されます。結果として、手や腕のしびれ、運動の制限、歩行に関する問題などの症状が現れることがあります。
外部サイトの関連記事:脳梗塞後の予後と生活の質(QOL)向上のためのポイント