<この記事を読んでわかること>
・片頭痛の病態がわかる
・片頭痛と脳梗塞の関係がわかる
・脳梗塞を併発しやすい片頭痛の前兆がわかる
片頭痛は周期的な頭痛やその他の随伴症状、前兆症状をきたす疾患であり、その病態には脳血管が関与していると考えられています。
そのため、同じく脳血管の病気である脳梗塞と一部関与があると言われており、片頭痛発作中に脳梗塞を発症する方もいます。
この記事では、片頭痛が原因で脳梗塞が発生する可能性やその前兆症状について解説します。
片頭痛患者が注意すべき脳梗塞の兆候とは?

片頭痛とは、その名の通り頭の片側(実際には両側痛くなることも多い)に拍動性のズキズキとした痛みが生じ、4〜72時間ほど経過すると自然に軽快するというのを繰り返す病気です。
また頭痛以外にも嘔気や感覚過敏、閃輝暗点(キラキラした光、ギザギザの光が視界に入る)などの症状を併発します。
(参照サイト:片頭痛|日本神経学会)
かの有名な小説家、芥川龍之介は、「歯車」という小説で閃輝暗点を歯車と名付けて一連の現象を記載したことも有名な話です。
片頭痛は基本的に命に関わるような病気ではなく、他の頭痛をきたす疾患(くも膜下出血や脳出血、髄膜炎など)とは一線を画す病気ですが、実は脳梗塞との関連性が示唆されています。
片頭痛も脳梗塞もどちらも病態に脳血管が関与していることから、両者は時に併発しやすいのです。
また、片頭痛には頭痛発作前の前兆症状を認めることがあり、Wolfらの報告によれば、片頭痛の経過中に脳梗塞を発症した事例で生じた前兆の症状として、下記のような症状を挙げています。
- 視覚前兆(閃輝暗点など)82.3%
- 感覚異常41.2%
- 失語症5.9%
このような症状を認める片頭痛の場合、脳梗塞を併発する可能性が高まるため注意が必要です。
(参照サイト:片頭痛と脳梗塞|J STAGE)
また、頭痛学会によれば片頭痛に伴う脳梗塞は特に若年女性に多く、前兆のある片頭痛患者においては脳血管障害のリスクが2倍になると報告しています。
(参照サイト:片頭痛性脳梗塞|頭痛学会)
以上のことよりも、閃輝暗点などの視覚症状や感覚症状、言語症状、ほかにも何らかの運動症状などを認める場合は注意が必要です。
片頭痛に関連する脳梗塞の種類:脳循環障害型の特徴
Wolfらの報告によれば、片頭痛に関連する脳梗塞は脳梗塞全体の0.21%で、そのうち病変部位は70.6%が後方灌流領域、29.4%が中大脳動脈領域でした。
また、特に経口避妊薬の内服者や喫煙者で有意に発症リスクが増大することが知られており、注意が必要です。
では、なぜ片頭痛によって脳梗塞が発症するのでしょうか?
いまだに原因が完全に解明されているわけではありませんが、片頭痛では脳血管において局所的な酸化ストレスを引き起こし、その際に脳血管内皮細胞が損傷すると考えられています。
その結果、血管内に炎症が生じて血栓が形成されやすくなったり、血管内腔が狭小化することで脳梗塞を引き起こしやすくなるわけです。
これに加え、経口避妊薬の内服は血栓を形成しやすくなり、喫煙者では血管内皮細胞がさらに損傷しやすくなるため、脳梗塞の発症率が増加すると考えられます。
(参照サイト:片頭痛と脳梗塞|J STAGE)
片頭痛と脳梗塞を予防するための生活習慣の改善方法
片頭痛はなかなか厄介な病気で、根治する方法に乏しく、日常的に内服薬を摂取して頭痛発作を予防する必要がありますが、それに加えて発作に伴い脳梗塞を発症すれば泣きっ面に蜂です。
そこで片頭痛の発作を予防するためには下記のような点に注意すべきです。
- 過度なストレスを溜め込まない
- 睡眠時間を確保し、規則正しい睡眠習慣を送る
- 人混みを避ける
- 過度な空腹やアルコール、カフェインの摂取は控える
- 強い匂いを避ける
上記の要因はどれも片頭痛の発作を起こしやすくする要因と言われており、発作予防のためにも上記のような要因を日常生活で極力避けることが重要です。
また、先述したように経口避妊薬の内服や喫煙も脳梗塞発症率を増加させるため、控えましょう。
また、片頭痛の発作を予防するのは当然ですが、脳梗塞そのものの発症予防も肝要です。
脳梗塞は、過剰な塩分や糖質・脂質の摂取などの不規則な食生活、運動不足、ストレス、飲酒や喫煙などで発症リスクが増加するため、片頭痛の発症予防とともに日常生活を見直すと良いでしょう。
まとめ
今回の記事では、片頭痛が原因で発生する脳梗塞について詳しく解説しました。
頭痛はさまざまな疾患で生じる症状であり、その中でも原因の1つである片頭痛は非常に緊急性の高い疾患というわけではないものの、長期的に発症者の生活を苦しめる厄介な病気です。
この記事でも紹介したように、片頭痛による血管内皮細胞の損傷によって脳梗塞を発症する可能性があるため、特にリスクの高い若年女性や喫煙者、ピル内服者は注意が必要です。
また、発作中に脳梗塞を発症しやすいため、日常生活では生活習慣を整えたり、睡眠を規則正しく取るなど、発作予防に努めることが肝要です。
もし仮に脳梗塞を発症した場合、対応が遅れれば重篤な後遺症を残したり、最悪死に至る可能性もあります。
現状では重篤な後遺症が残った場合に改善する術はリハビリテーション以外になく、仮にリハビリテーションを行なってもこれらの後遺症を根治することは困難です。
一方で、近年では片頭痛に伴う脳梗塞の後遺症に対する新たな治療法として再生医療が大変注目されています。
ニューロテックメディカルでは、「ニューロテック®」と呼ばれる『神経障害は治るを当たり前にする取り組み』も盛んです。
「ニューロテック®」では、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供しています。
また、神経機能の再生を促す再生医療と、デバイスを用いたリハビリによる同時治療「同時刺激×神経再生医療Ⓡ」によって、これまで改善の困難であった脳梗塞に伴う後遺症の改善が期待できます。
よくあるご質問
- 片頭痛を放っておくとどうなる?
- 片頭痛は基本的に治療せず治る病気ではないため、放置すると症状が遷延、重症化し、日常生活にも大きな支障を与えます。
頭痛という身体症状はもちろんのこと、ストレスによる精神不安や、健康寿命の短縮など、さまざまな弊害が生じるため注意が必要です。 - 片頭痛は脳梗塞になりやすい?
- 片頭痛は脳梗塞になりやすいと言われています。
明確な機序は判明していませんが、特に前兆を伴う片頭痛の発作中に脳梗塞になる割合が多いようです。
どちらも同じ脳血管の異常を伴う病気であり、なんらかの関連性が示唆されます。
(1)顔面神経麻痺|日本頭蓋顎顔面外科学会:https://jscmfs.org/general/disease13.html
(2)脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2023〕|日本脳卒中学会:https://www.jsts.gr.jp/img/guideline2021_kaitei2025_kaiteikoumoku.pdf
(3)顔面神経麻痺に対するリハビリテーションの進め方|J STAGE:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jibiinkoka/124/7/124_954/_pdf
関連記事
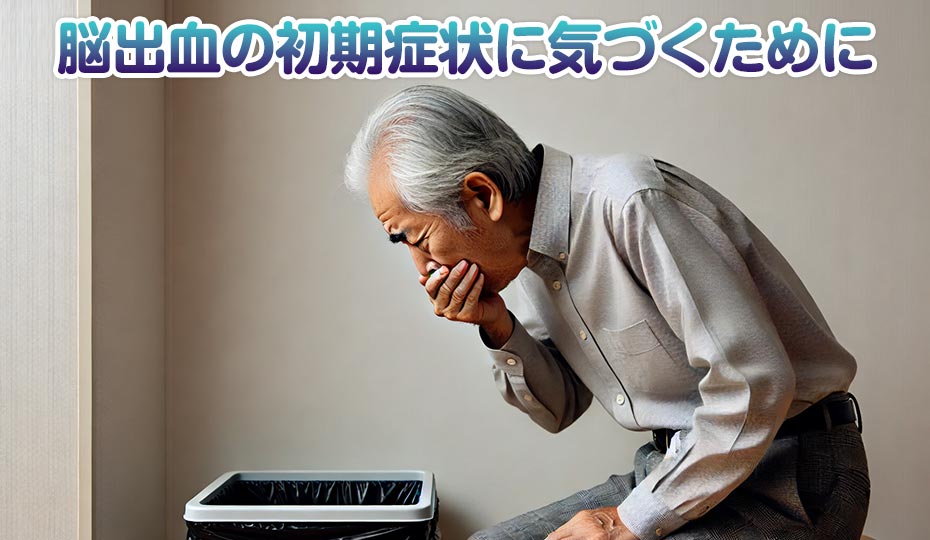
脳出血は、早期に発見し適切な対処を行うことが、命を救い、後遺症を軽減するためにはとても重要となります。しかし、その初期症状は他の病気と見分けにくい場合もあります。この記事では、脳出血の初期症状に気づくためのポイントと、その際の適切な対応について詳しく解説します。

脳梗塞は高齢者だけではなく、若い世代でも発症する可能性があります。初期症状として、一時的な手足のしびれや麻痺、言葉が出にくい軽度の失語症、視野の片側が欠ける視覚障害などが挙げられます。これらは脳の異常を示す重要なサインであり、放置すると症状が悪化するリスクがあります。適切な予防と早期対応が、健康を守る鍵となります。
外部サイトの関連記事:脳梗塞かも?チェックリストと応急処置








